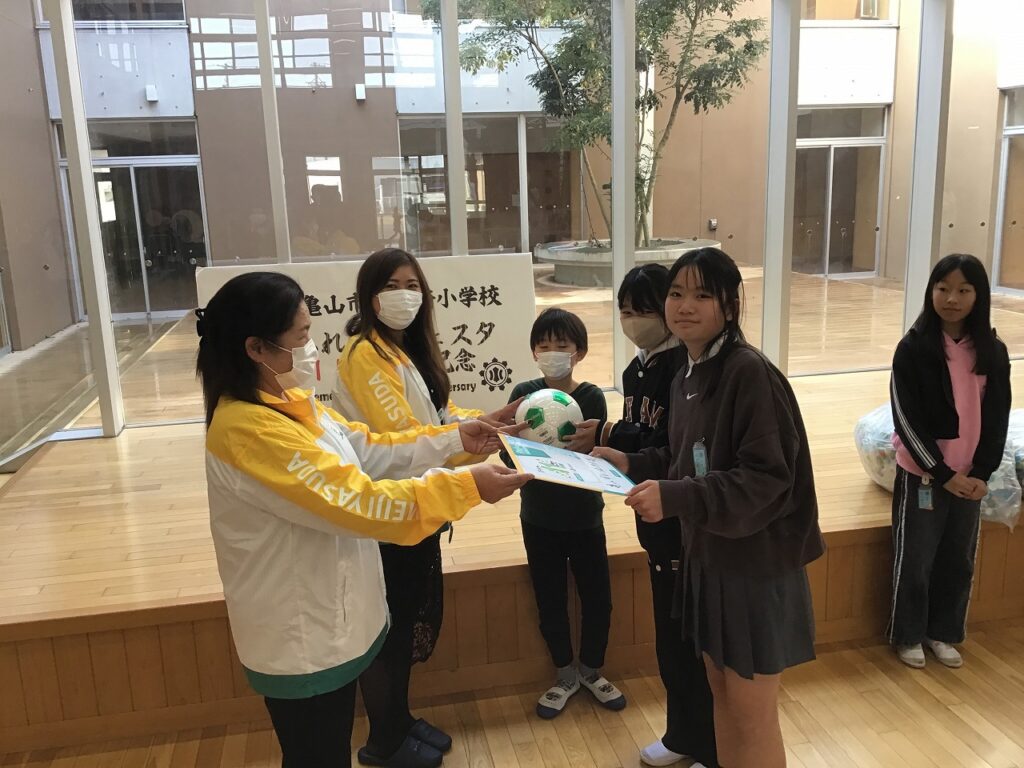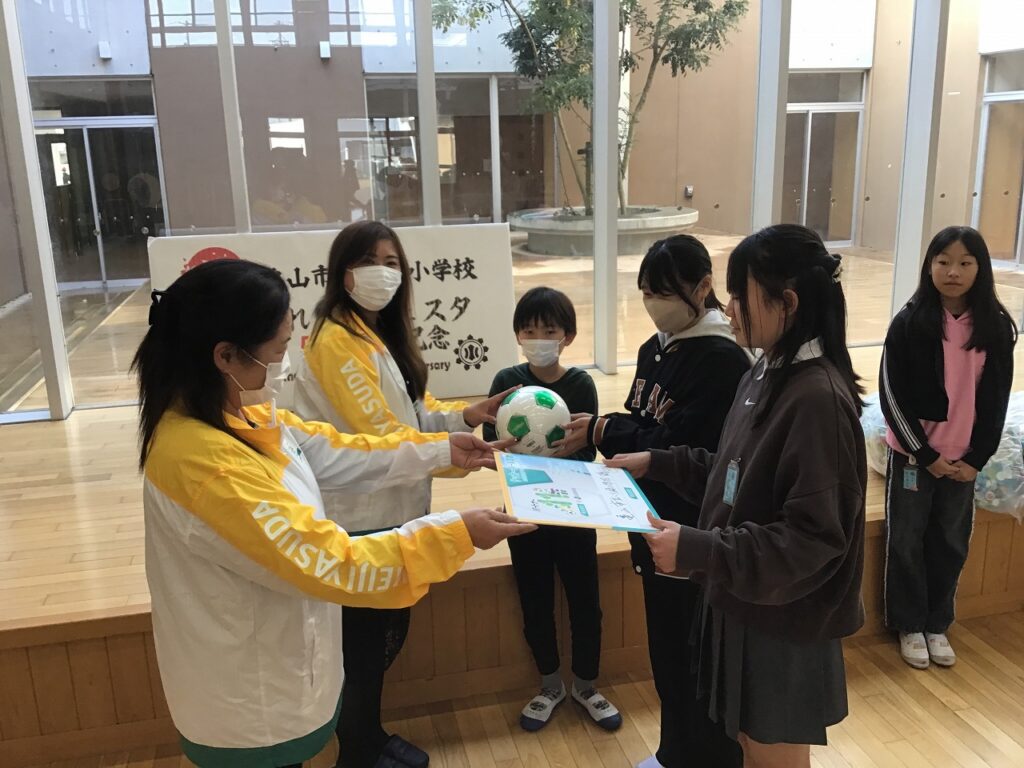12月10日の3・4限目に4年生が三重県の防災教育支援事業として、防災教育の授業を受けました。県の学校防災アドバイザーの方を講師としてお招きし、防災についての授業をしていただきました。
1つ目の授業は、自然災害にはどんなものがあるのか、地震が起きるメカニズムや洪水が起きた時どうするとよいのか等を資料や動画を使いながら、わかりやすく教えていただきました。
2つ目の授業は「防災すごろく」をグループで体験しました。すごろくをして、防災についての問題を考えながらゴールを目指しました。楽しみながら協力して防災について学ぶことができました。
今後も災害について備えるととともに、命を守るために自分で考え、最善の行動ができるように防災についての学習を進めていきます。
ご多用のところご指導いただきました三重県教育委員会の学校防災アドバイザーの方々ありがとうございました。