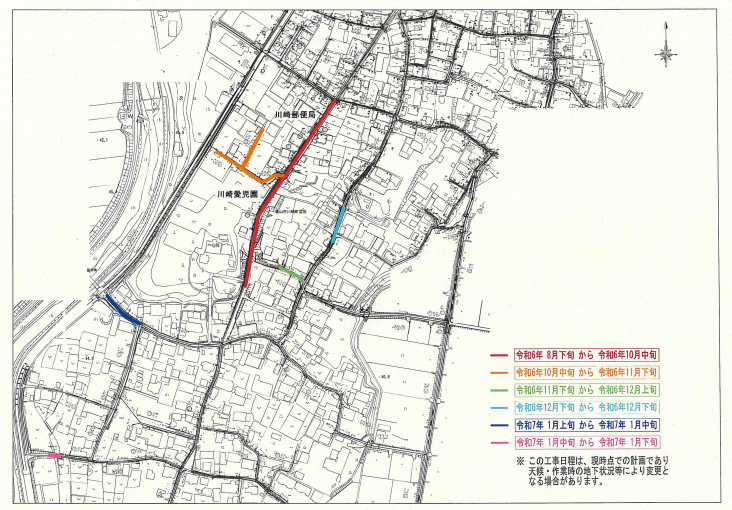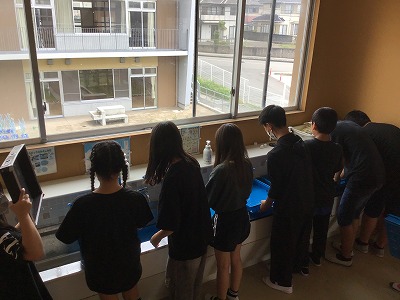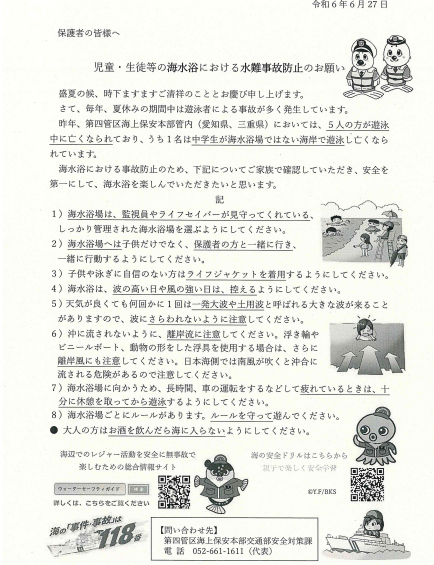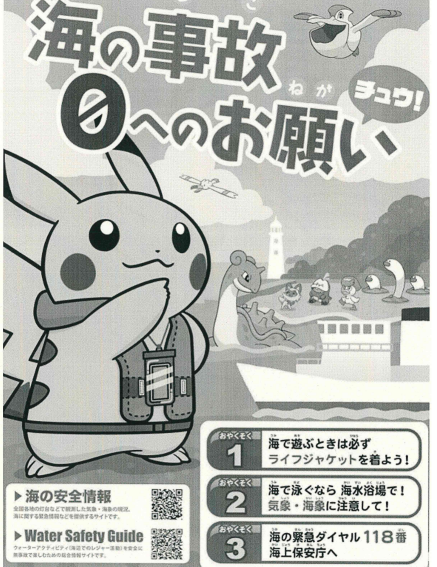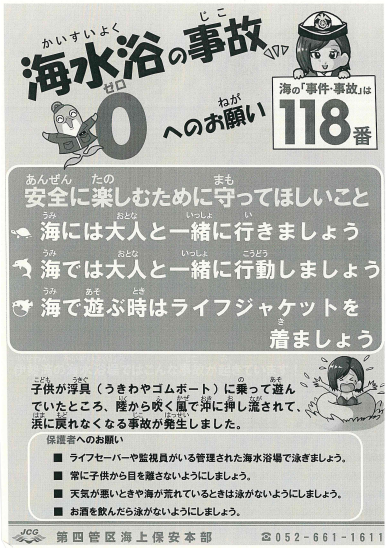台風10号の影響が心配されましたが、おかげさまで、本日から無事2学期が始まりました。長い夏休みを経て、学校に子どもたちの声と笑顔が戻ってきました。子どもたちは久しぶりの学校で友達と会って、元気な様子を見せてくれました。学校に子どもたちの活気が戻ったことを嬉しく思います。始業式は校長からの話、生徒指導担当からの話、教職員の紹介、教育実習生の紹介、転入児童の紹介、表彰伝達を行いました。新しい出会いと頑張りをたたえる拍手の多い素敵な始業式になりました。
さて、2学期も引き続き保護者や地域の皆様のご協力の下、教職員一丸となって子どもたちと学びを進めてまいります。夏休み中も新型コロナウイルスなど感染症が流行しました。2学期も、子どもたちの体調管理にご協力ください。
また、長かった夏休み明けの時期ですので、「規則正しい生活」ができるよう、毎日しっかり食事をとり、早寝早起きで十分睡眠をとるよう、おうちでもお声かけください。よろしくお願いいたします。