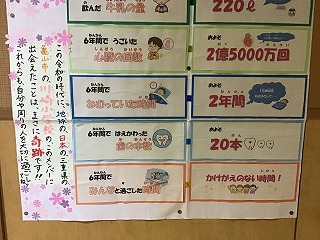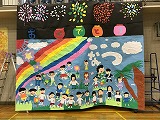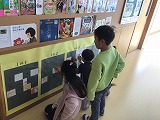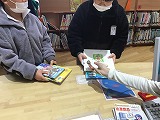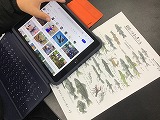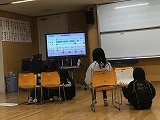令和7年度新たなスタートです。保護者の皆様、地域の皆様には平素から学校行事をはじめ様々な教育活動にご理解とご協力をいただいていますこと、心より感謝申し上げます。
さて、4月7日に着任式・始業式を行いました。16名の教職員が本年度着任しました。子どもたちは、新しい学年に進級し、意欲と希望にあふれています。この1年間の成長が楽しみです。
教職員一同、川崎小学校の歴史と伝統を継承しつつ、子どもたち一人ひとりが日々成長できる学校を目指して、全力を尽くしてまいります。
ご承知の通り、子どもは学校教育だけで成長するわけではありません。本年度も引き続き、学校・家庭・地域が「チーム川崎」となって、子どもたちの輝く未来のために、ご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。