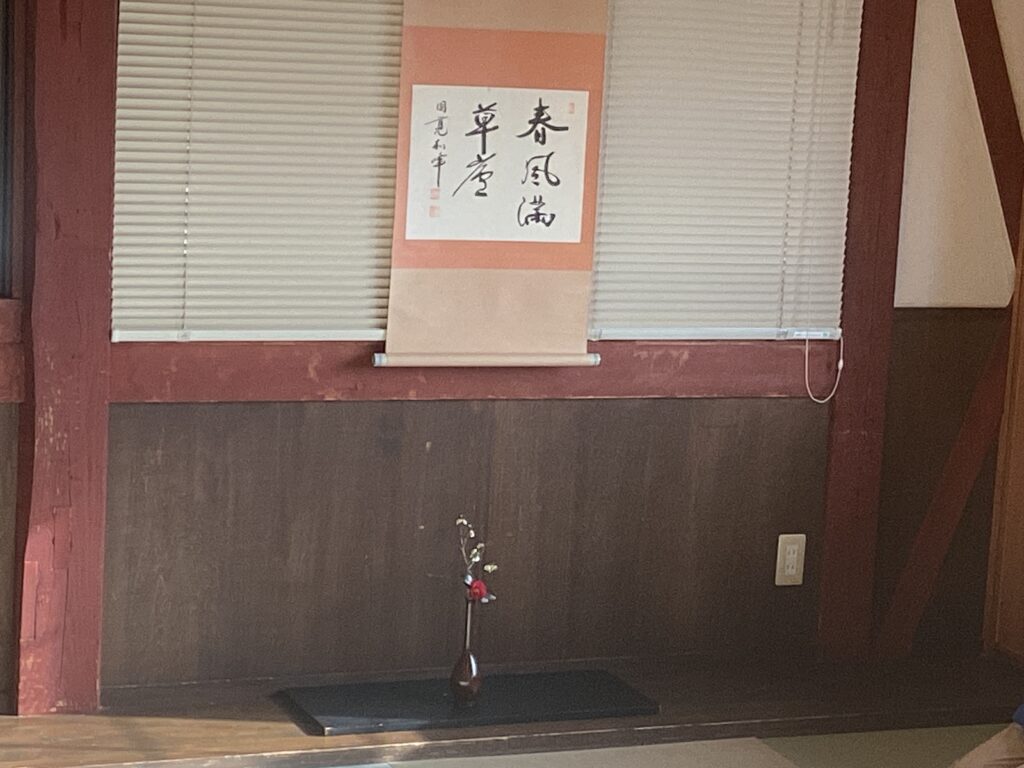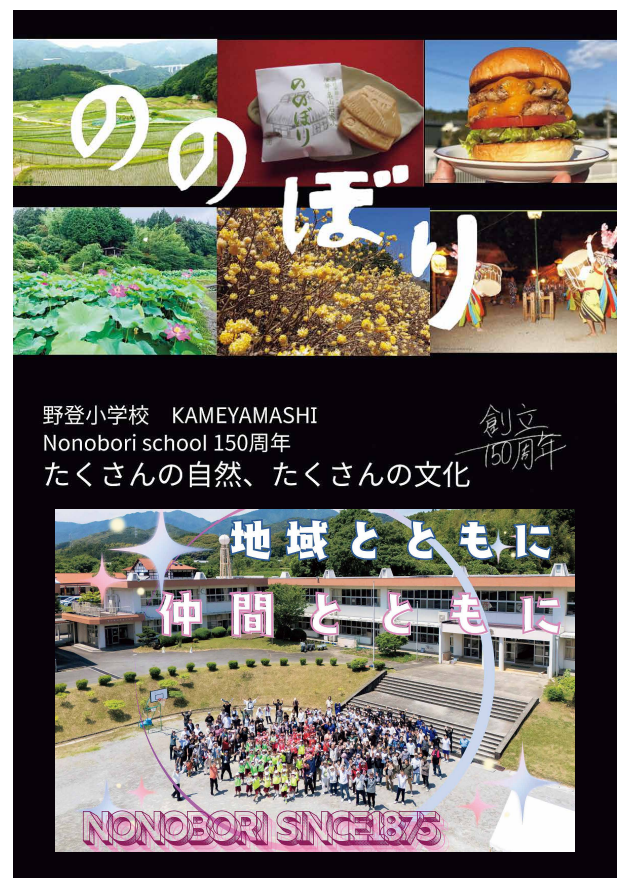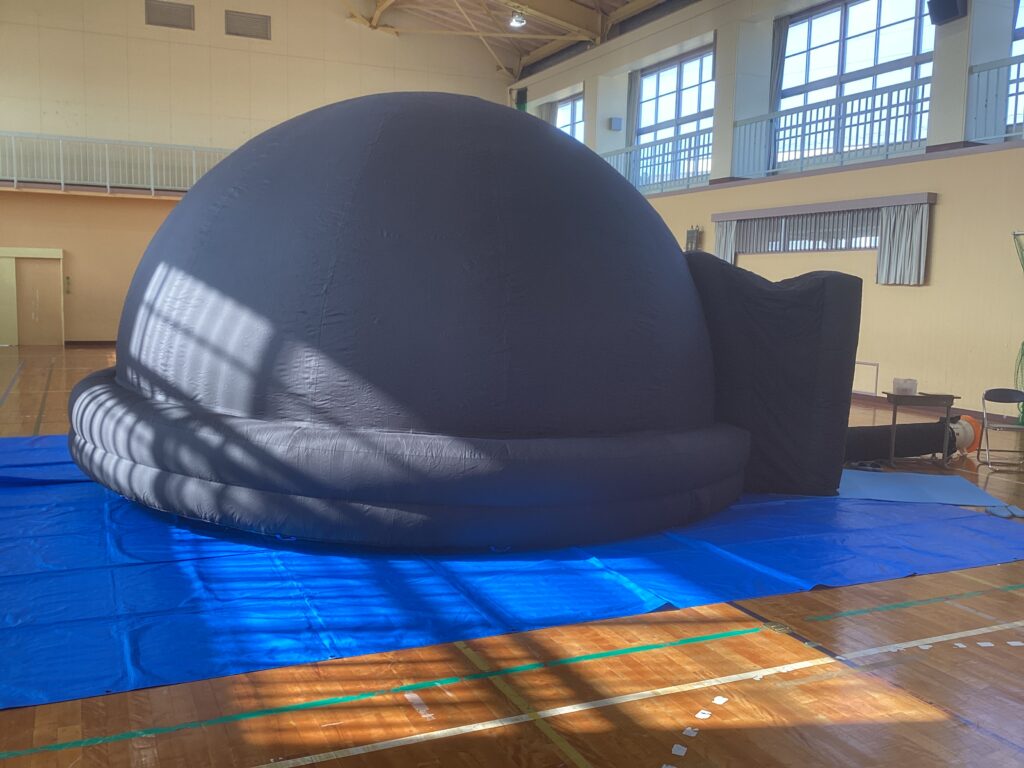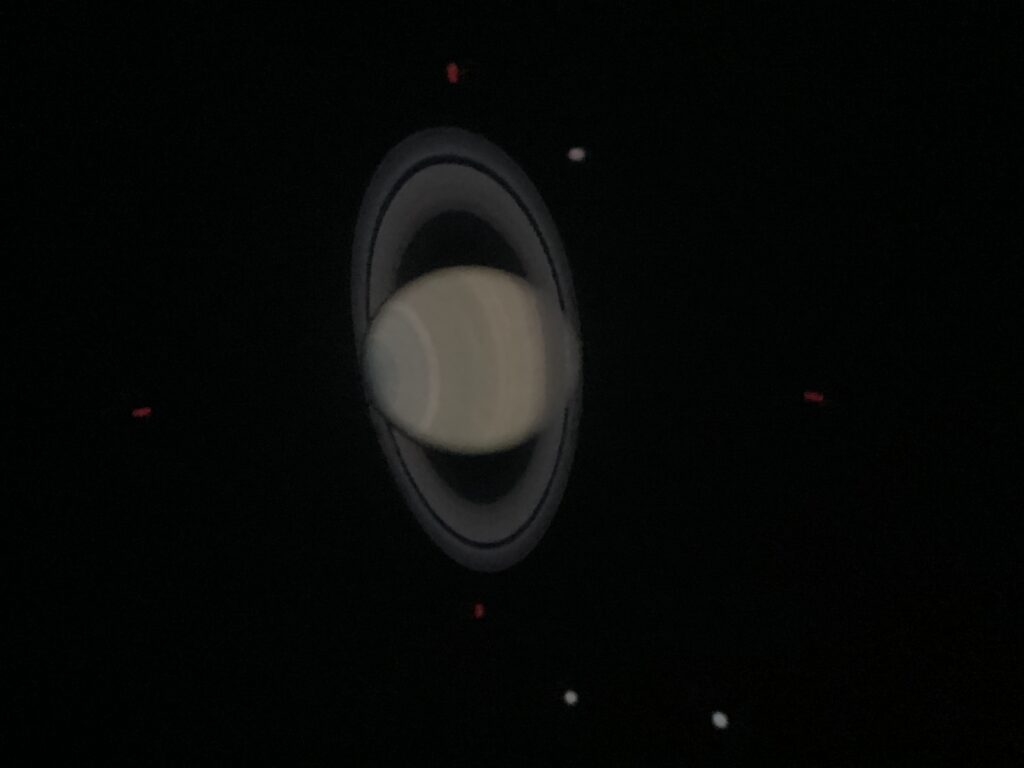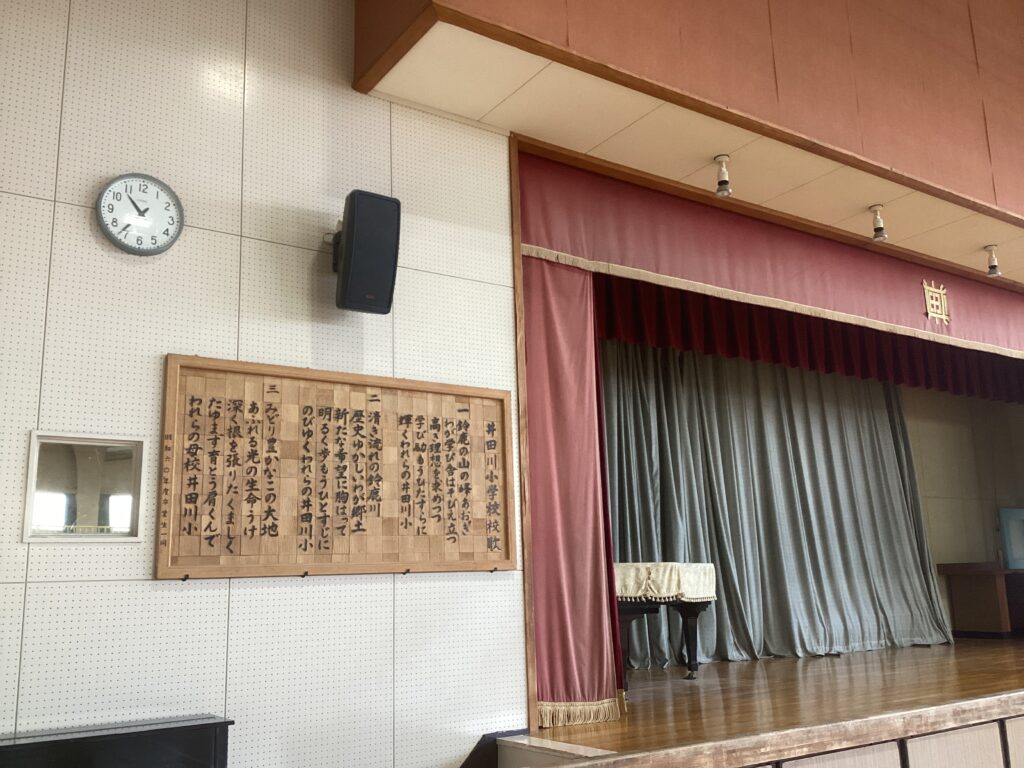2月25日、本校の6年生が川崎小学校に行き、川崎小学校の6年生と交流会をもちました。本校は児童数が少ないため、6年生が中学校入学後に中学校生活を円滑にスタートできるよう、同じ中学校区内の井田川小学校・川崎小学校と交流会をもっています。今回は、川崎小学校との交流会です。川崎小学校のみなさんには、会場を準備したり、交流会の内容を考えたりと、大変お世話になりました。本校の6年生の子どもたちは、最初は少し緊張した表情がありましたが、交流がすすむにつれて、笑い合う声や協力して活動する姿が見られるようになりました。最後には、「また会おうね」と中学校入学後の再会を約束する姿がありました。中学校に入学してからも、今回の交流会のように、お互いに名前を呼び、声をかけあい、協力し合う「仲間」になってほしいと思います。4月に、また笑顔で会える日が楽しみですね。