1月の献立表を掲載します
2学期終業式
12月22日(金)2学期の終業式がありました。とても大切な節目の式なので、静かに始まりました。
節目の式には校長の話がありますが、今日は終業式の話(概要)をお伝えします。

長かった2学期も今日で終わりです。終業式にはいつも数字の話をしますが、今日もいくつか数字もあげてお話をします。
2学期に学校の授業があったのは77日でした。しかし、学級閉鎖などで4年1組を除いてそれよりも少ない日数になりました。4年1組で欠席がなかった人が一番多く学校に来たことになります。
2学期でぜひとも身につける2つのめあてがありました。1学期からのめあてとして「人の話をきちんと聞く」もう一つは2学期にお話しした「あいさつをする」です。何度も繰り返しお話をしているので覚えていると思いますが、どちらも人を大切にする人しかできないことです。これからも続けてめあてにしていきます。
そして、3学期の話です。3学期は2学期と比べて短く、6年生は49日、そのほかの学年は51日登校する予定です。1つの学期ごとに1つめあてを追加してきましたが、今までの2つのめあてができる人が増えましたので、3学期には「ルールを守る」というめあてを追加します。新しい「ルールを守る」というめあてについて、詳しくは3学期の始業式にお話をしたいと思います
そして、待ちに待った冬休み。今年の冬休みは17日あります。クリスマスや正月があったり、旅行や帰省などで出かけたりする人もいることでしょう。健康や安全に気を付けて、3学期の始業式には全員が元気にそろって登校できることを願っています。
学級閉鎖の基準と学校からの情報提供について
12月21日(木)2学期も残すところ今日も含めてあと2日となりました。2学期の大きなできごとを振り返るにあたり、真っ先に思い浮かぶのがインフルエンザの大流行です。
10月の下旬からおよそ1か月の期間に全校で160名ほどの児童がインフルエンザにかかり、4年1組を除くすべての学級が順番に閉鎖となるなど今までに経験がないほどの大流行となりました。県内ではその後に大流行が発生していますが、本校ではこのところ出席停止と病欠を合わせても10名以下となっており、病気による欠席は少ない状況を保っています。
では、改めてどのような基準で学級閉鎖を行っているか説明をいたします。法的にはこの割合を超えると閉鎖するといった明確な基準はありません。これは、学級人数が5人程度といった小規模校もあるため、閉鎖の基準を2割とすると1名欠席したら学級閉鎖となり、そのようなことから一律に決めることができないためです。
本校では、国や県、市の通知等を参考に、学級の人数の2割がインフルエンザにかかっている(検査などが受けられない場合もあるのでインフルエンザとみなされている数を含む)と判断された場合は学級閉鎖を検討します。出席停止が2割に満たない場合も病欠や発熱早退が相当に多い場合は、その人数も加味して検討することがあります。
その日の欠席状況等を学校医に相談し、専門的な見地からご助言を頂き、さらに出席停止が見込まれる場合などは学級閉鎖としています。
本校ではインフルエンザの感染症が増えている場合、学校ホームページで情報の速報を行い、出席停止や病欠の人数、学級閉鎖となったクラスや期間なども詳細に報告してきました。現在のように感染症が落ち着いている場合は特に報告は行っていませんが、感染症が急増している、出席停止が10名を超えている、学級閉鎖が発生している場合等はこれからも速報で情報提供を行ってまいります。(状況の変化があった場合は、1日に何度も更新をしていきます)
本来はこれからが寒さの本番でインフルエンザの流行期に入ります。2学期の状況を見ればインフルエンザの感染力はあなどれず、相当に強力なものがあり、あっという間に家族全員が感染したという事例もあります。また、インフルエンザの型は複数種類あり、何度もインフルエンザにかかるということやコロナとの同時感染もあるなど、心配な情報も入ってきています。
先日もメール配信で感染症の防止について情報提供を行いましたが、今後におきましても感染症の未然防止に努めていただくとともに、発熱等があった場合は早期の受診等、適切な対応をお願いいたします。
プレゼント
校長室には打ち合わせや相談など学校の先生がいつも出入りしています。そして、先生だけでなくいろいろな来客があります。
業者の方や工事関係の方。地域の方や保護者の方。市役所や教育委員会の職員。亀山東小学校の児童も学習の聞き取りや質問(インタビュー)、時には相談や教室で落ち着けないなどの理由で訪れることがあります。
中には、プレゼントを持って訪れてくれる児童もいます。
「今度販売するアロマキャンドルの試作品が完成したので持ってきました。」とか、「メダルを作りました。」「クリスマスプレゼント!」「手紙を書きました。」など・・・

おそらく、このようなプレゼントを受け取ることは厳密にいうとだめなのでしょうが、お話を聞きながら受け取ると、みんなとてもすてきな笑顔になります。こちらも心から嬉しいので笑顔になります。
コンプライアンスから言えば「受け取れません」というのがルールなのかもしれません。しかし、どのような気持ちで持ってきてくれたのかを考え「ありがとう、うれしいなあ。」と正直な気持ちを伝えて受け取っています。
校長の仕事は学校の管理が中心で、本来子どもと直接かかわることは少ないのですが、なるべく多く教室をまわり、いろいろな子どもの様子を見て、声を聞き取り、充実した学校生活を送れるように願っています。
そして、私のことを気にかけてくれる子がいたり、このようなプレゼントを頂いたり、そのようなできごとはなによりのごほうびとなっています。
今年最後の給食
今日は12月19日(火)、今年最後の給食です。
毎年、子どもたちは何かの特別献立があるととても楽しみにしていますが、今日は「亀山っ子給食」と「クリスマスこんだて」の実施日です。
献立表を見ると、「スパイスチキン」「ミルストローネ」「かめやま茶パン」「クリスマスデザート」とあります。
文字で見るとおいしそうな感じはしますが、よくわからないですよね。なので、百聞は一見にしかず。写真でご確認ください。

通常は、個人情報の保護の観点から、画質を落とし、写真のサイズも小さくしていますが、今日は大きくしても影響がない(むしろよくわかる)ので、大きいサイズでお届けします。(スマホの場合は指でピンチアウトすれば写真が大きくなるように設定してあります)
ミルストローネには星形にくりぬいた野菜がたくさんあって、にぎやかです。スパイスチキンはいつものから揚げよりも、少しだけピリッとしています。
もう少しパンチがあってもよいのですが、1年生も同じメニューなので万人向けのおいしさになっていました。
かめやま茶パンは少し緑色。お茶の粉末を練りこんで作ってあります。安定のおいしさです。
そして、謎なのがクリスマスデザートです。写真を見ればはっきりと・・わかりませんね。パッケージがかわいいのは伝わると思います。中身は3層のババロアとゼリーでした。衛生的に配膳する必要があるのでこのようなデザートになりました。また、このデザートのすごいところは、クリームやババロアに乳や卵を使用していないところです。アレルギーの子でも食べられるよう、美味しさと優しさがつまったすてきなデザートです。
先日、ある保護者の方に「ミルストローネ」が好きなので子どもから作ってほしいと言われ、作ってみたが「給食のミルストローネと違う」と言われてへこんだというお話を聞きました。トマトベースの野菜煮込みという感じですが、少しでも雰囲気が伝われば幸いです。
学校だより 2学期末号
学校だより2学期末号をアップします
図書館のかざり作り
12月14日木曜日、業間と昼休みを利用して図書館のかざり作りがありました。
今回担当したのは3年生と4年生の希望者です。

絵やかざりを作るのが好きな人が集まっていましたので、できの方は上々でした。

すてきなかざりがたくさんできました。

最終的にはこの窓に掲示しますが、たくさんかざりができたので、きれいにかざるには工夫が必要です。

皆さん楽しみにしていてくださいね。
※2学期も授業のある日は毎日(日によっては複数回)更新してきました本校ホームページですが、2学期の主な学校行事はほとんど終わり、現在学期末のまとめの時期を迎えています。今後更新をお休みする日がありますがその点をご了解ください。
12月とちの木集会
12月13日水曜日、5限目にとちの木集会がありました。
今日の校長の話は「ふたご座流星群」の話でした。
毎年、この時期にはふたご座流星群の観測が適期を迎え、多くの流星を見ることができると思います。特に今日は月の影響を受けにくく、空気が澄んでいるので星空を見てみるのもよいかもしれません。
夕方は東の空、真夜中は天頂、明け方は西の空で流星が見られる確率が高いそうです。この記事を18:00くらいに書いていますが、先ほど5分ほど東の空を見ていたら1つ流星を見ることができました。
児童会会長の話は「東っ子まつり」のお礼でした。その中で売り上げの報告がありましたが60,470円にもなりました。その資金を元に、これから4年ぶりに開催される亀山大市の準備をしていくという説明でした。
とちの木集会の今月の発表は3年生と4年生で、総合的な学習で調べたことをクイズなどにまとめ、3年生は学校や校区内について、4年生はいろいうな仕事について発表しました。


よく通る大きな声で、内容もとてもしっかりとした発表でした。
うれしい悲鳴
とちの木集会では、各種表彰を受けた児童について学校でもそのがんばりをたたえて紹介をしています。
毎回集会前には表彰を受けた児童が多くても集会がスムーズに進行できるよう、名簿をきちんと整理してから臨むようにしています。
それにしても皆さんのがんばりがすごかったせいか、コロナ禍を経て各種行事や大会が戻ってきたせいか、すごい数の賞状やたてなどが集まっており、うれしい悲鳴をあげながら整理しているところです。

前回も30名ほどの表彰がありましたが、集会が近づくと校長室のたなは賞状などで占領されます。皆さん、今回もがんばりましたね。
環境学習とリサイクル工作
12月も半ばに差し掛かりましたが、連日汗ばむような陽気が続いています。
そのように書くとよい事のように思われますが、「これでよいのか」「冬に車のエアコンを冷房にセットするくらいの高温が続いているが、地球は大丈夫か」と考えてしまいます。これも地球温暖化が影響しているのではないでしょうか。
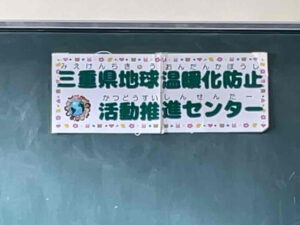
12月8日(金)と12月11日(月9の2日にわたり、2年生を対象に地域のボランティアの先生をお招きして、環境学習とリサイクル工作を行いました。

まず始めに地球温暖化の原因やその影響を学びました。
本来いなかった生き物が定着し、栽培する作物やとれる魚の変化など、ここ数年で明らかに地球環境が異変をきたしています。それらのことを2年生でも理解できるように、事例を交えて説明して頂きました。
その中には自分たちでも実践できることがたくさんありました。
お話の後はリサイクル工作です。今回は牛乳パックを使った「ルービックキューブ」の制作です。

作るのは比較的簡単で、その後遊ぶのもおもしろい工作でした。どれくらいの時間で絵がそろうか競争したりして遊んでいました。

環境教育はそれぞれの発達段階で取り組んでいます。難しい問題ではありますが、まずは楽しく学ぶことが環境問題を考える入り口になると考えています。
