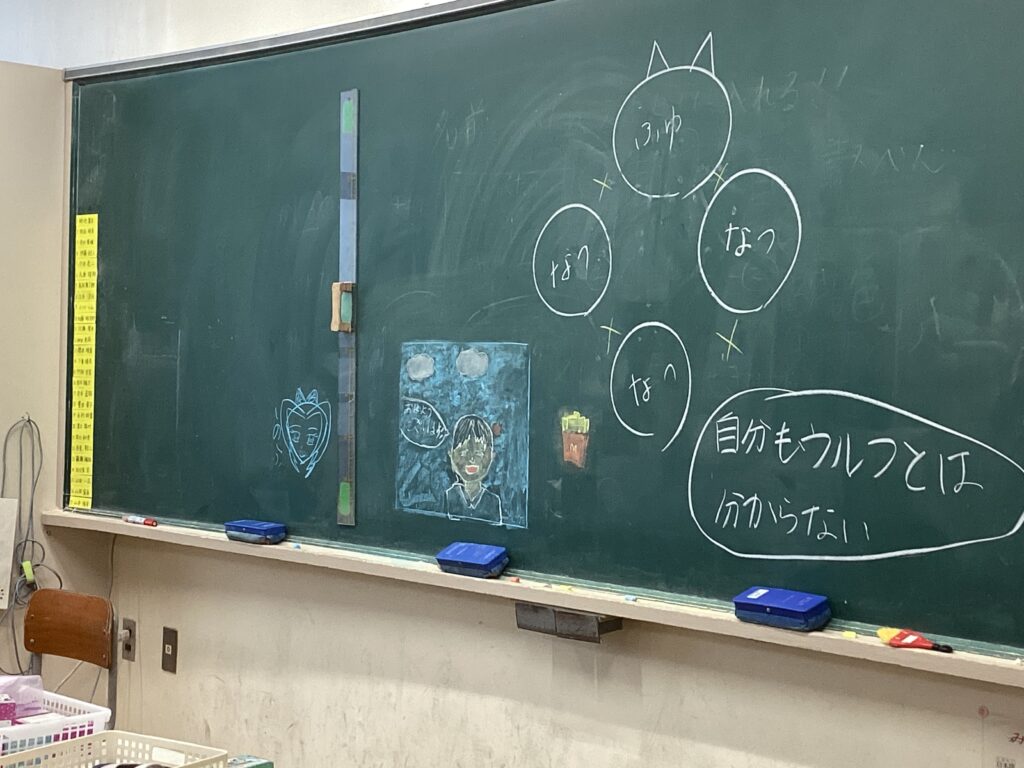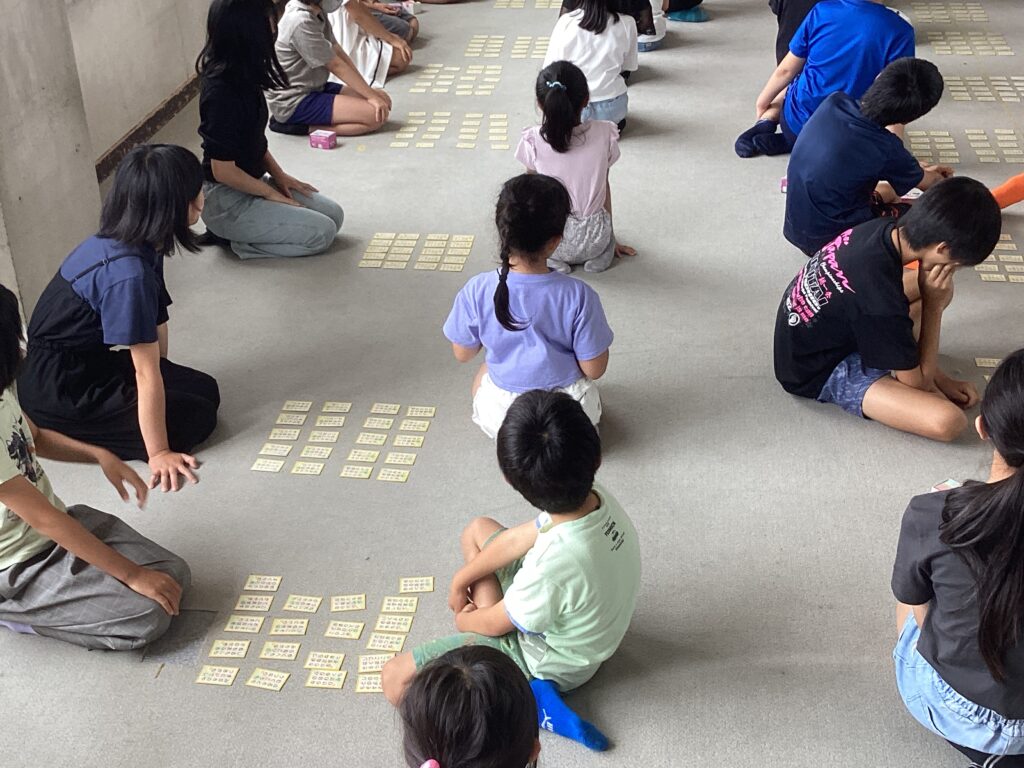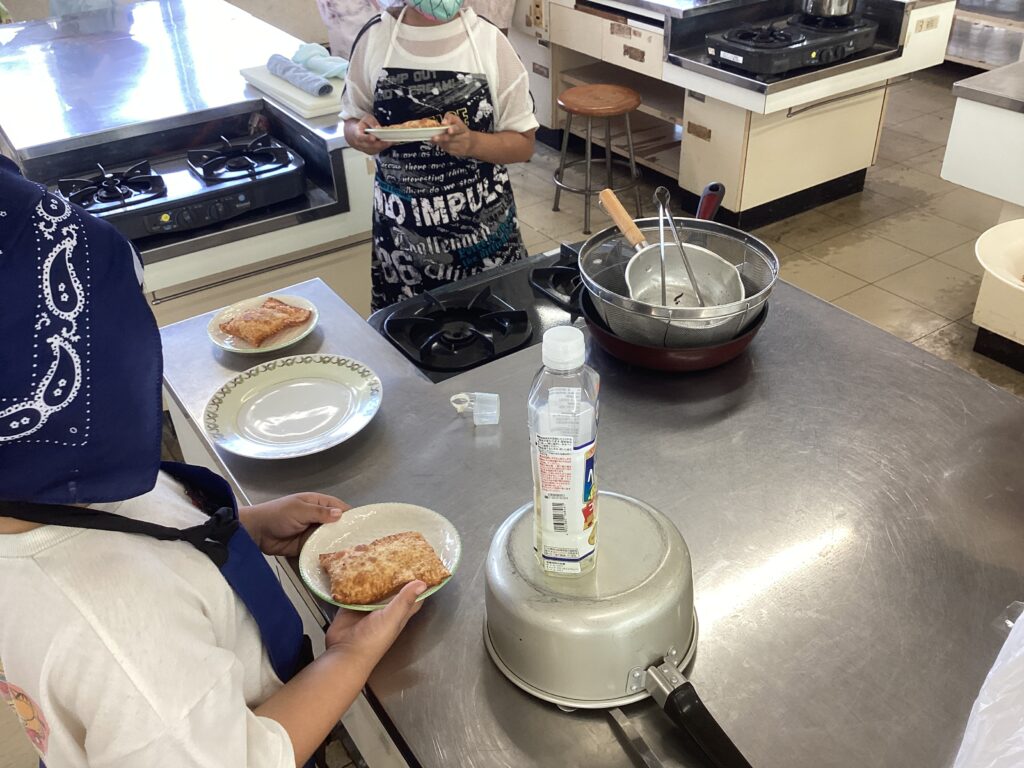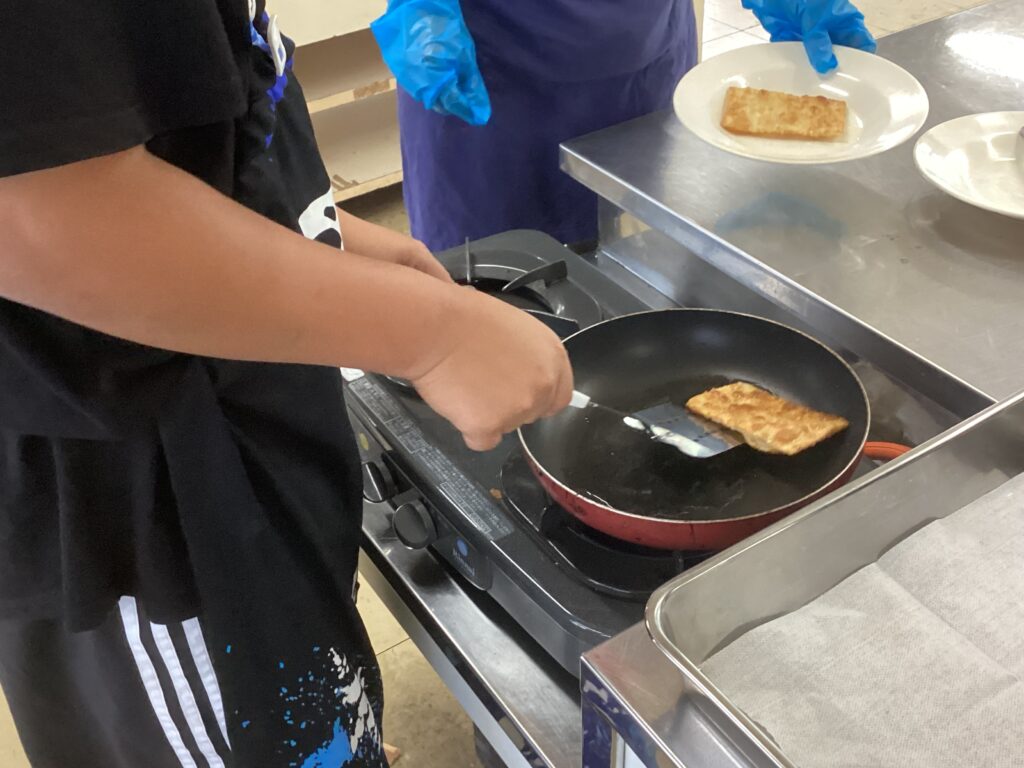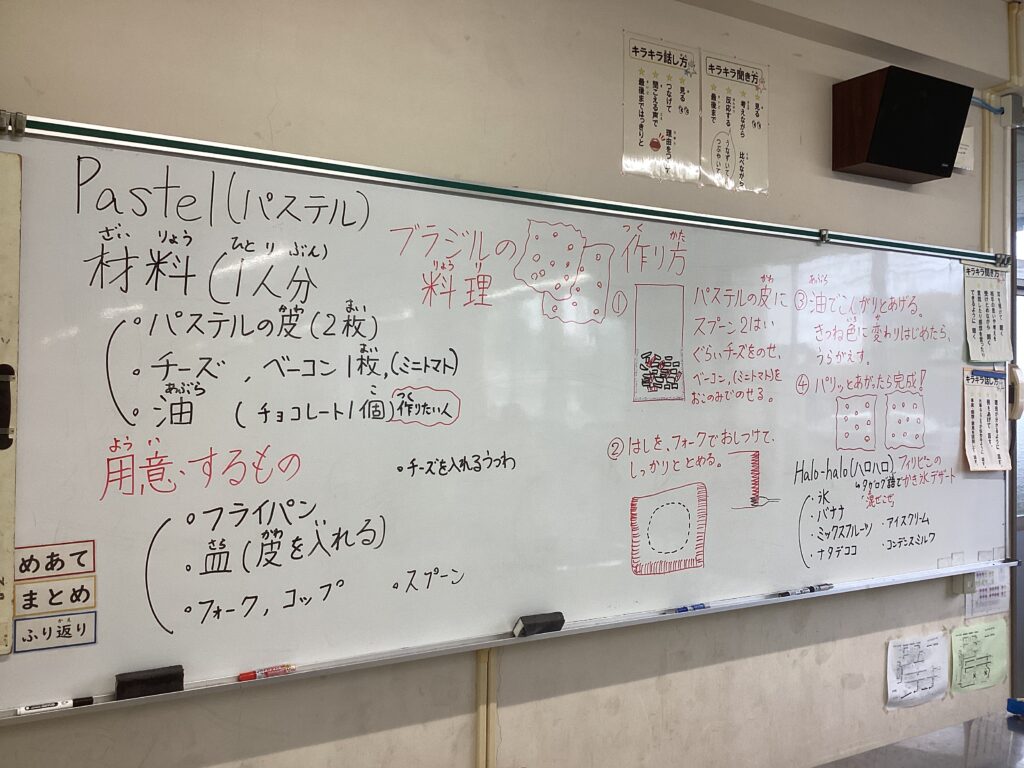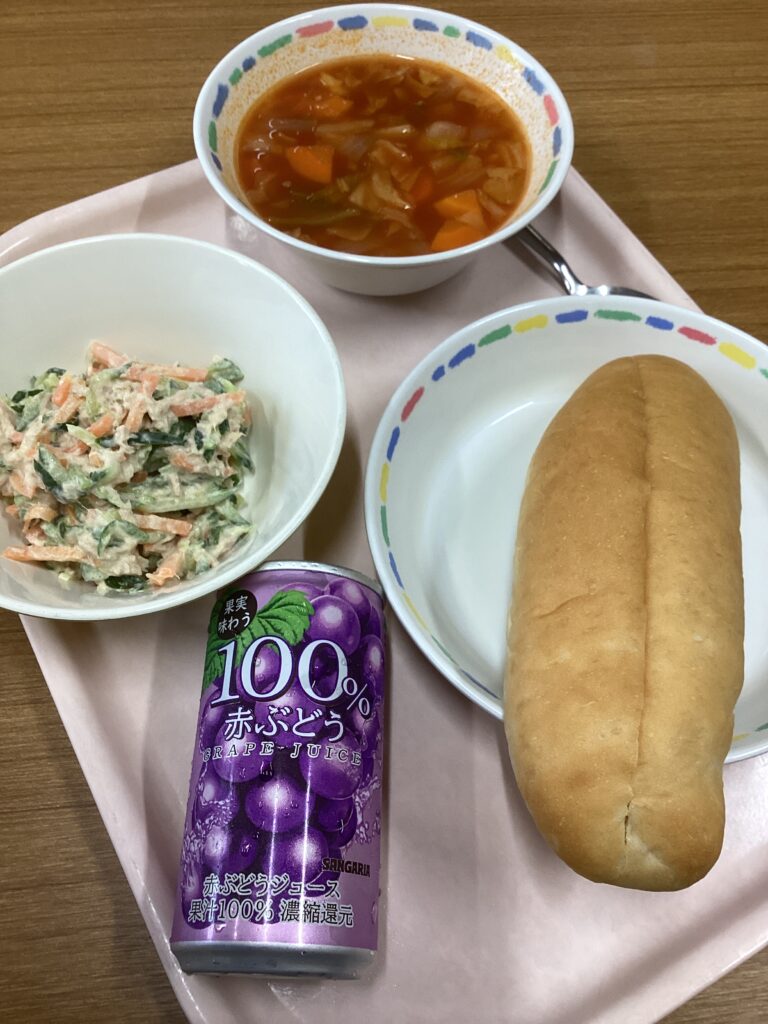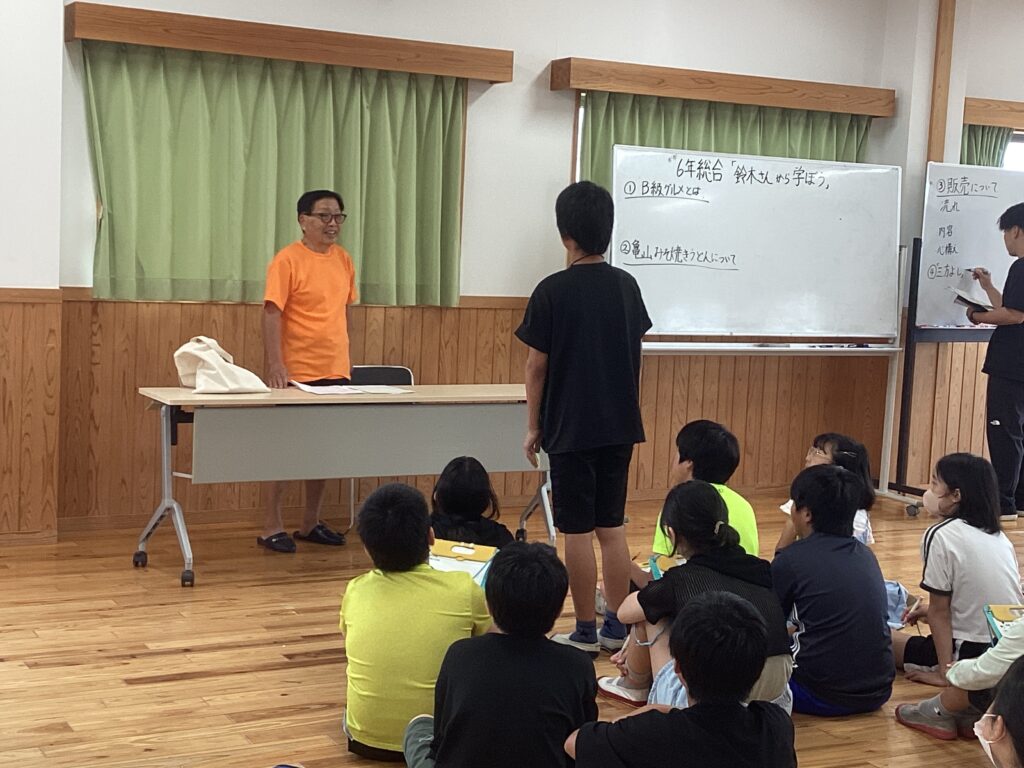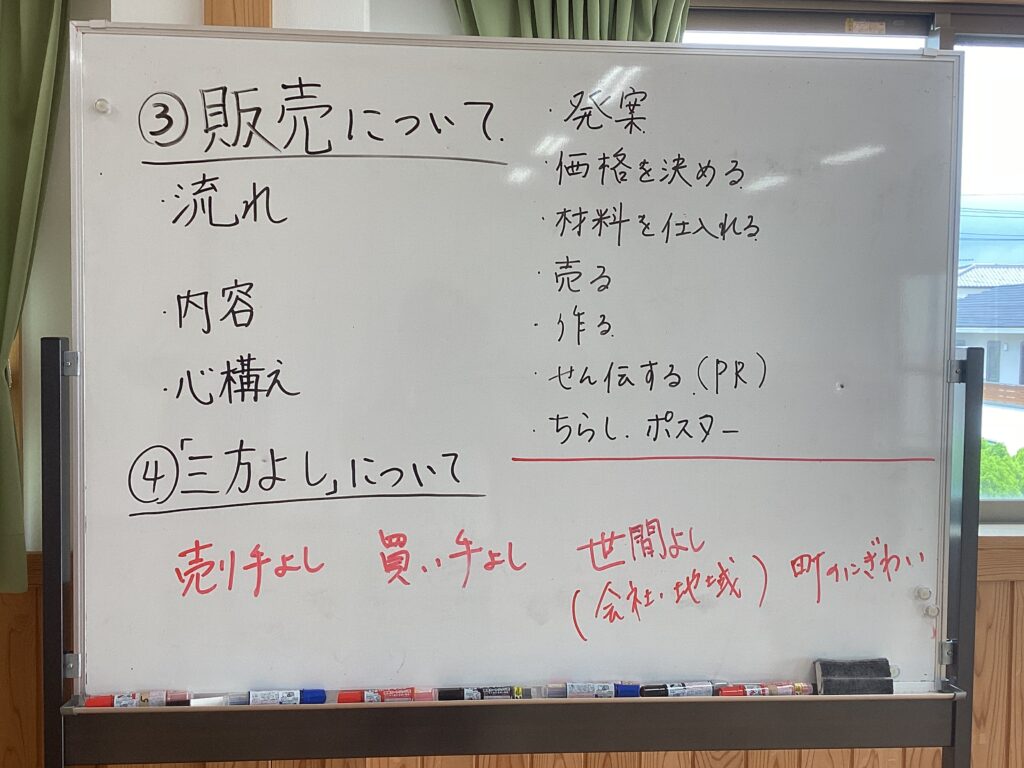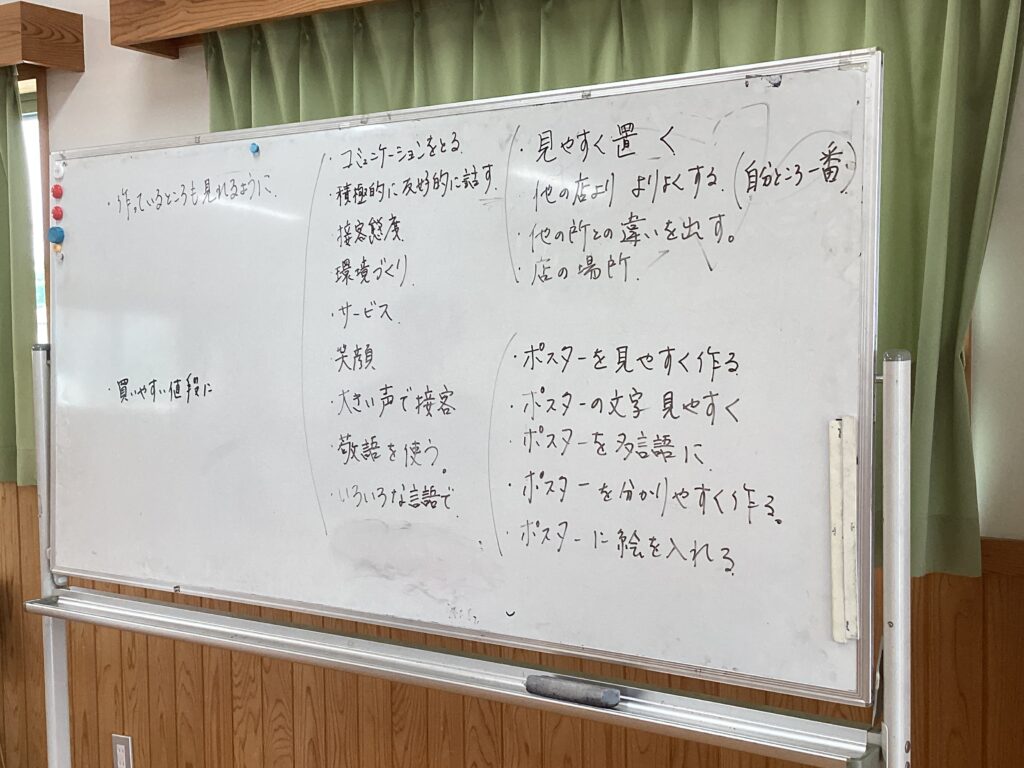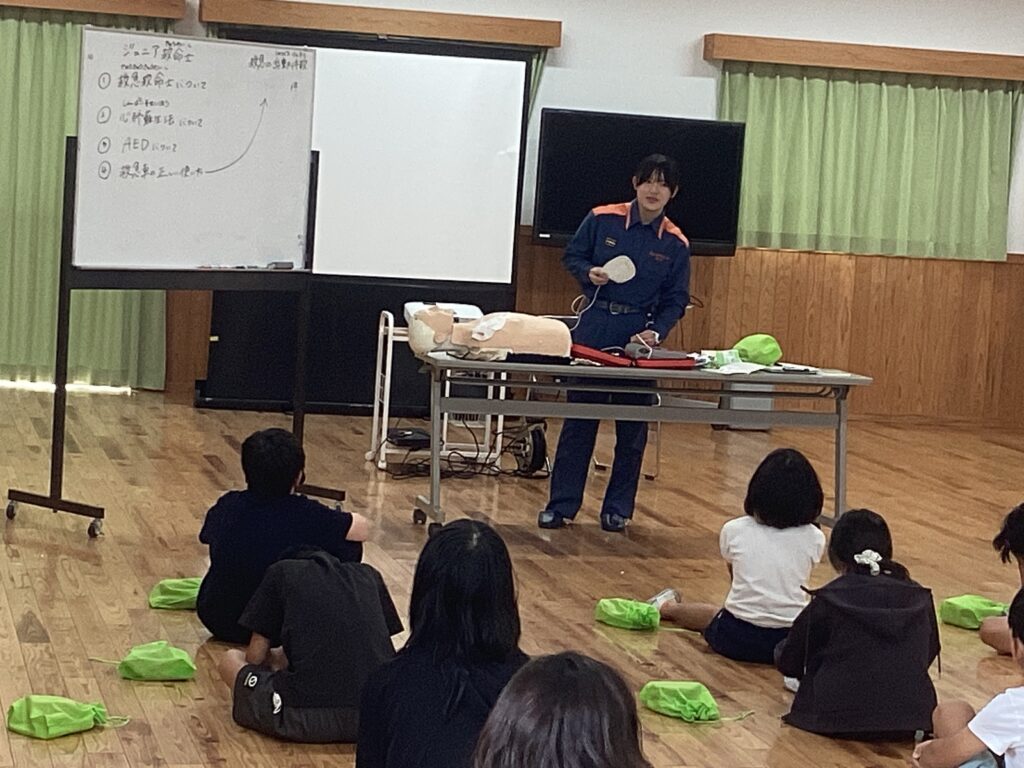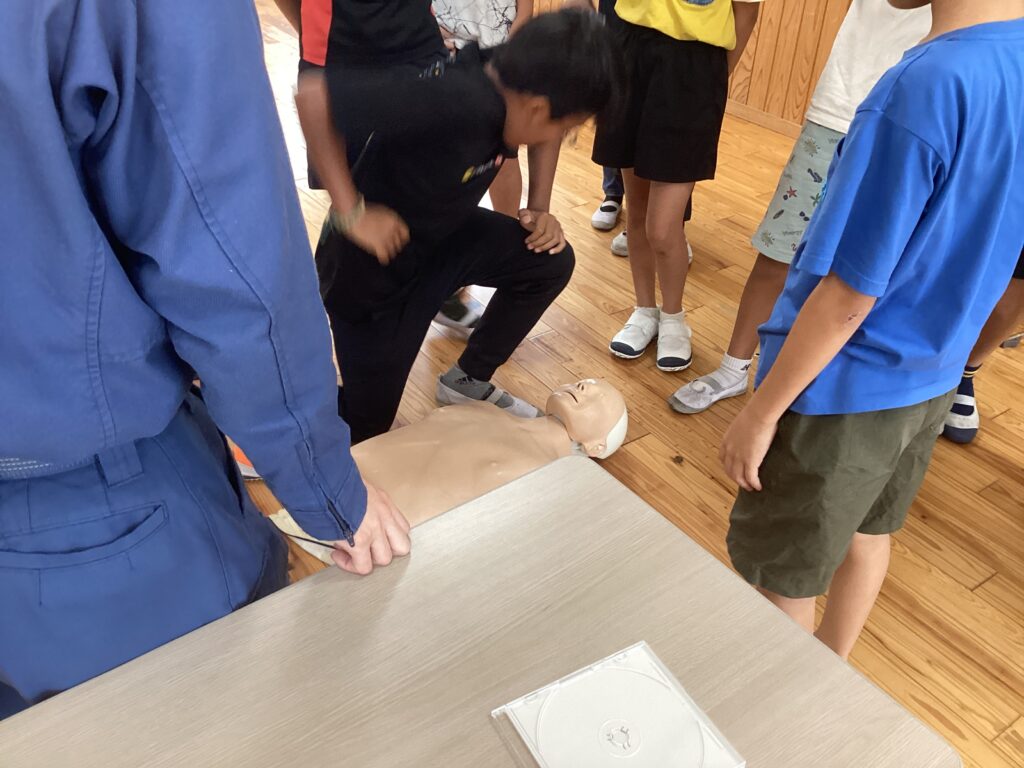9月1日(月)、2学期の始業式をおこないました。
校歌斉唱、校長の話、生活の話、着任職員の紹介、という内容でした。
校長の話としては、「きょう、もしかしたら『学校に行きたくないな』と思った人もいたかもしれないけど、よく登校してくれました。ありがとう」というところから、3つの話をしました。以下のような内容です。
最初は、今日が「防災の日」ということ。今まで、「防災」といえば、地震や大雨のことを中心に考えていましたが、今年は、「暑さ」も災害のうちのように思います。今朝、交差点で皆さんの登校のようすを見守りましたが、帽子をかぶっていない子がたくさんいて、心配になりました。これからも当分の間、朝、帰り、ともに暑くなると思うので、帽子、日傘(隣や前後を歩く子もいるので、持ち方には気をつけましょう)、冷感タオル等(濡らして振ると冷たくなるものなど)を、うまく活用しましょう。
ふたつめは、コミュニケーションの話です。「大阪・関西万博へ行ったひと」「海へ行ったひと」「バーベキューをしたひと」「回るお寿司を食べたひと」「お墓参りに行ったひと」「映画館へ行ったひと」「スイカ割りをしたひと」「流しそうめんをしたひと」など、夏休みにした体験を、ぜひ語り合いましょう。遠くへ行ったから偉いとか、自慢とか、そういう話ではなく、誰のどんな体験も貴重なので、相手を尊重してしっかり聞き、話しましょう。
最後は、ここには詳しく書きませんが、防犯の話です。みんなを守るため、気をつけたいことについて話しました。
生活指導担当からも、3つの話がありました。
あいさつの話は、地域の方を含め、「大きな声で」「自分から」あいさつができると素敵だという話でした。
次に、「いじめのない学校にする」という話がありました。いじめは絶対に許されないことであり、相手の体や心を傷つける行動のないようにしなければならないこと、困ったことがあればおとなに相談してほしいことといった話でした。とても大切なことです。
3つめは、「学校をぴかぴかに」という話でした。なかでも、特にトイレの美化に努めてほしいという話でした。
新しく着任された先生の紹介については、授業は3・4年生を担当してもらいますが、全校のみなさんと一緒に活動するのでよろしくお願いしますということでした。
今日の始業式は。予定の時刻より前に全校の児童が揃い、きちんとした姿勢で待つことができたため、早く始めることができました。すばらしい2学期のスタートとなったと思います。