◎2025(令和7)年4月10日(木)

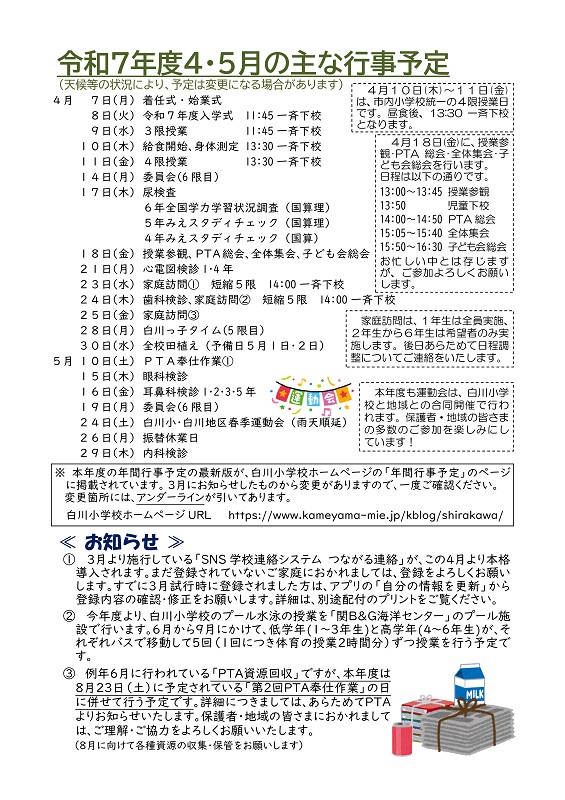
学校だよりのpdf版は、「学校からのたより」内の「明星<学校だより>」のページをご覧ください。

1年生に学校を案内しました
◎2025(令和7)年4月9日(水)
4月9日(水)3限目、6年生児童が1年生児童を連れて白川小学校の校舎内を歩き回り、各学年の教室や特別教室、更衣室、児童トイレの場所などを案内しました。お兄さん・お姉さんに手をつないでもらって校舎をまわりながら、1年生の子どもたちは物珍しそうにあちらこちらを眺めていました。
令和7年度入学式を行いました
◎2025(令和7)年4月8日(火)
4月8日(火)10:00から体育館にて「令和7年度入学式」を行いました。本年度の新入生は4名です。6年生児童に手をつながれて入場した新入生は、名前を呼ばれると大きな声で返事をし、在校生からの「歓迎のことば」に対しても大きな声で「よろしくお願いします」と応えていました。運動場の桜も満開に咲き誇り、新しい1年生の入学を祝福しているかのようでした。新入生4名を含む40名の「白川っ子」の一年間がスタートします。学校と家庭と地域とで子どもたちを見守り育て、子どもたちのより良い成長に力を尽くしていきたいと思いますので、どうか皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
令和7年度のスタートです
◎2025(令和7)年4月7日(月)
4月7日(月)、いよいよ令和7年度がスタートしました。体育館で行われた着任式では、新しく白川小学校に赴任された先生方の紹介が行われ、子どもたちは興味津々な顔で先生たちからの挨拶に聴き入っていました。続いて行われた始業式では、校長より「いよいよ新しい1年間のスタートです。昨年と同様、たくさんチャレンジしてたくさん失敗して、その失敗からたくさん学んでください。失敗なくして進歩はありません。失敗したときに励まし支え合える仲間であるために、日頃から相手の気持ちを考えた発言や行動ができるようにしていきましょう。新1年生が明日入学しますが、良いお兄さん・お姉さんとして、下級生の面倒をしっかり見てあげてください。みんなで、いい白川小学校をつくりあげていきましょう。」との話がありました。最後の担任の先生の発表では、担任の先生の名前が告げられるたびに、子どもたちから歓声があがっていました。まずは4月、緊張感をもって良いスタートをきっていきましょう!
令和6年度修了式を行いました
◎2025(令和7)年3月25日(火)
3月25日(火)、体育館で令和6年度の修了式を行いました。全員で校歌を歌った後、校長から「一年の締めくくりの式が修了式です。この一年間、失敗を恐れずにチャレンジできましたか? 失敗を失敗で終わらせるのでなく、自分の成長につなげることができましたか? 失敗を笑うのでなく、互いに励まし合い応援し合える仲間でいられましたか?」と問いかけがありました。春休みを利用して、自分の一年を振り返るとともに、新しい一年のスタートに向けて心の準備をしていきましょう。学習したことについても復習して、忘れたところや理解できていなかったところは学びなおしておくと良いですね。続いて、生活指導担当の先生や養護の先生からも、「時間の過ごし方と心の安全・身体の安全」について話がありました。春休み中も、病気・怪我や事故などないように気を付けて、生活リズムをくずさず安全に過ごせるよう家庭での見守りをよろしくお願いします。
◎2025(令和7)年3月24日(月)

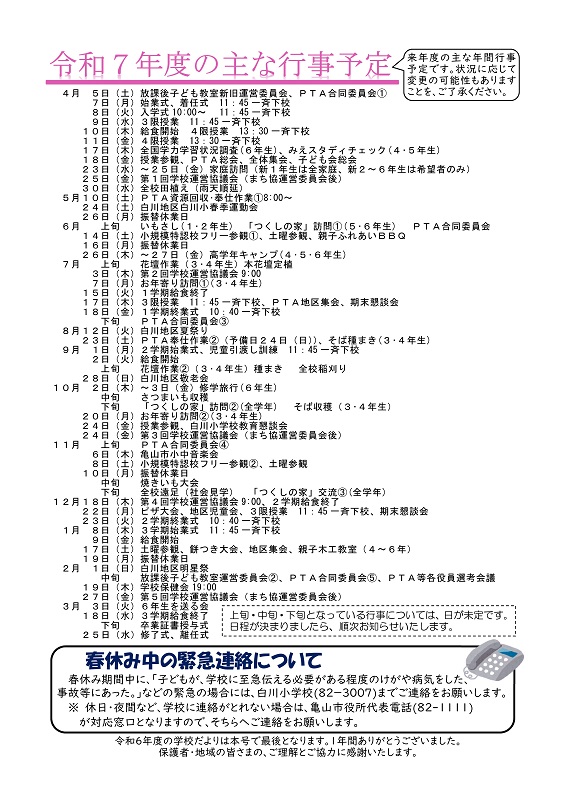
令和6年度卒業証書授与式を挙行しました
◎2025(令和7)年3月19日(水)
3月19日(水)、体育館にて「令和6年度卒業証書授与式」が行われました。雪まじりの雨が降る肌寒い日となりましたが、体育館の中はぴりっと引きしまった空気が流れていました。来賓の皆さまや保護者・在校生が見守る中、卒業生が入場し、一人ひとりが自分の夢を語って卒業証書を受け取ると、それぞれの保護者に感謝の気持ちを込めて卒業証書を手渡していました。風の音や雨の音で、歌や呼びかけの言葉が聞こえにくい場面もありましたが、気持ちのこもった良い式でした。式中の「学校長のことば」では、「百聞は一見にしかず」ということわざへの疑問を投げかけ、「同じ景色を見て同じ時間を過ごしていても、何が見えてどう感じているのかは、一人ひとりの生まれや経験によって違う。中学校でこれまでよりもはるかに多くの人たちと同じ時間を過ごすことになるけれども、誰もがあなたと同じようにものを見て、同じように感じるわけではないのだから、お互いの違いを認め、理解するよう努めることがとても大切である。」という内容の話がありました。卒業生の皆さんが、中学校で良い人間関係をきずき、さらなる成長と活躍をすることを期待しています。頑張れ、白川小学校卒業生!
卒業を前に…
◎2025(令和7)年3月14日(金)
3月14日(金)5限目に6年生の子どもたちが、古くなった児童トイレの「スリッパをそろえるための目印の図柄」を新しいものに作り直してくれました。卒業を前に、自分たちにできることを探して、考えて動いてくれました。ありがとう!
卒業式に向けて練習中です
◎2025(令和7)年3月11日(火)
3月11日(火)4限目、体育館で1~5年生が来週の卒業式に向けて歌と「別れの言葉」の練習に取り組んでいました。歌詞や言葉がまだあやしい子もいて、まだまだ練習が必要な様子ですが、卒業式まで一週間…。ぜひ、お家でも頑張って練習してきてくださいね。
「全校遊び」と「白川っ子タイム」を行いました
◎2025(令和7)年3月10日(月)
3月10日(月)、昼休みに「6年生との思い出を作ろう!」と体育・放送委員会が企画して「全校遊び」を行いました。種目はドッジボールです。なかよし班の1・3班vs2・4班の対戦で、子どもたちはコートを行ったり来たりしながらソフトバレーボールを投げ合っていました。また、5限目には体育館で「白川っ子タイム」が行われ、児童会から2・3月の目標の反省と代表委員会からの報告があった後、新旧の児童会役員さんからの挨拶がありました。最後に全員でグランドに移動し、児童会企画の「しっぽとり」で運動場を走り回りました。なかよし班4チームの対抗戦で、1・2年生のつけた黄色いしっぽは1ポイント、3・4年生の赤いしっぽは2ポイント、5・6年生の青いしっぽは3ポイントとして互いのしっぽを取り合い、グランドには子どもたちの歓声が響いていました。今年度もあと二週間ですね。「終わりよければすべてよし」という言葉もあります。いい1年の締めくくりにしていきましょう!