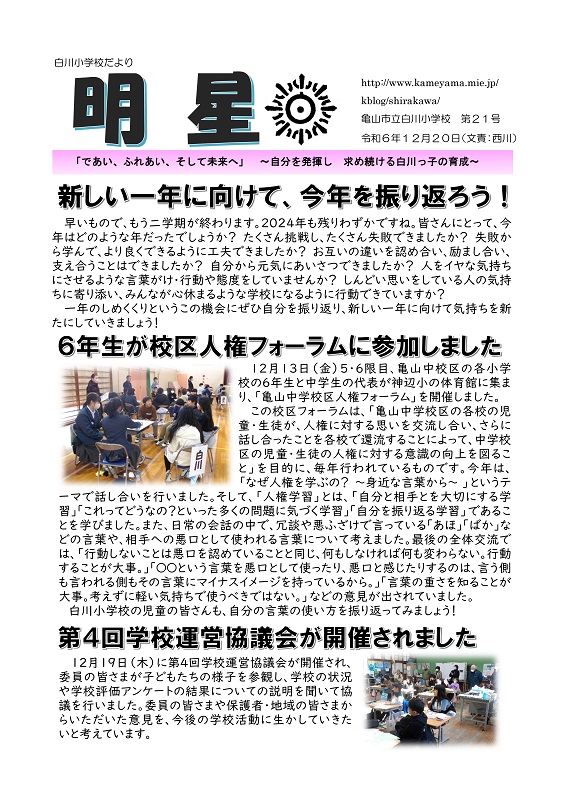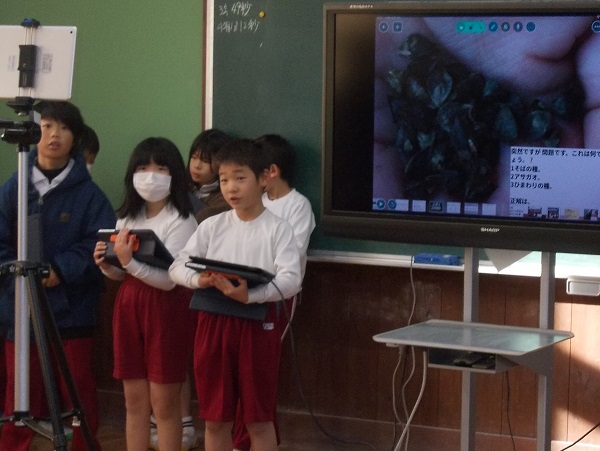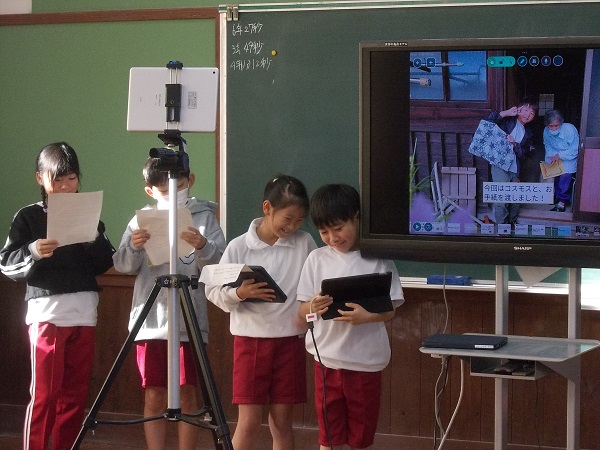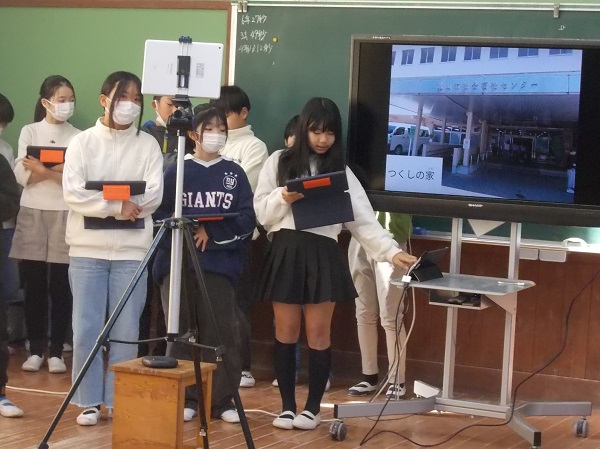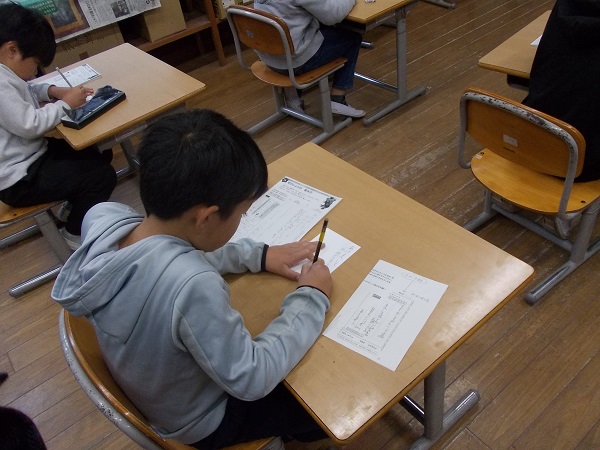◎2024(令和6)年12月24日(火)
前回の「炭の窯出し」の際に、空いた窯に並べられた原木は、年明けに火入れを行う予定でしたが、急遽予定を変更し12月22日(日)から4回目の炭焼きを開始し、12月23日(月)の夜に「窯止め」を行いました。このまま、二週間ほどおいて三学期に入ってから最後の「窯出し」を行う予定です。今回で本年度の「炭焼き」は終了です。炭焼き講師の浅野重信さん・川合正男さんをはじめ、たくさんの地域の方々の協力で事故や怪我もなく今年も無事に炭を焼き上げることができました。ありがとうございました。