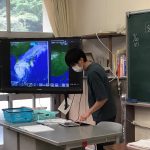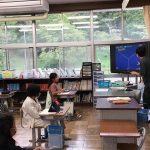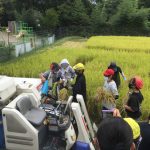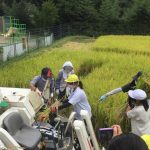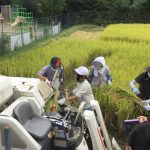社会科の授業で4年生は「自然災害とわたしたちのくらし」を学習しています。亀山市でも地震や水害など大きな自然災害が起こったことを学んだ子どもたちは、各家庭でどのような災害対策をしているのか調べ、写真に撮ってきました。授業では、自分たちが調べてきたことをグループで互いに発表し合い、「今やっている自分の家の災害対策で本当に命を守れるのだろうか」というテーマで話し合いました。「ハザードマップがあるけど、今のではなく、昔のものだから常に新しいものにしていかないといけない。」「いろいろ必要な道具が入っているけど、使い方がわからないと意味がない。」「ヘルメットがあるけど、家族の人数分必要だよね。」「非常食があるけど、賞味期限が切れている。」「いろいろ入っているけど、いざという時に何が入っているのかすぐにわかる必要があるのではないだろうか。」などと、写真を見ながらしっかり考え、気づいたことを話し合っていました。救援活動が受けられるまで、必要なものを各家庭で備えておくことは大切なことです。日頃から一人ひとりが防災意識をもって防災学習を進め、自分たちにできることを考えていきたいと思います。