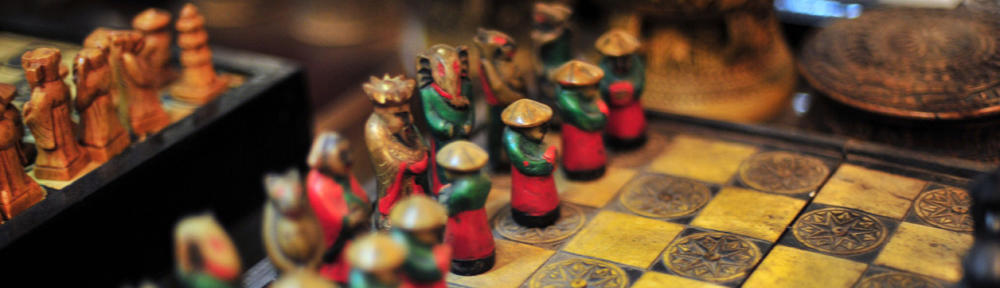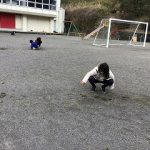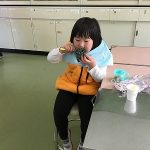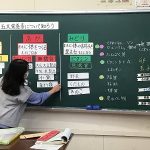小学校から中学校への進学で、子どもたちは三つの大きな環境の変化に遭遇します。まずは、①大きな校舎、広い運動場などに移ることによる物的な環境変化、②新しい先生、新しい友だちなどに出会う人的環境変化、③新しい規則、雰囲気などのなかに入っていく社会文化的変化です。また、小学校の学級担任制から教科担任制への移行も子どもたちには大きな段差となります。そこで関中学校校区では小中連携事業の取り組みとして、計画的に中学校の先生に来てもらう出前授業を来春入学する6年生向けに行っています。
3月14日の3限目に関中学校の先生にお越しいただき、実際に体育の授業をしてもらいました。さすが体育の専門家ですので、見本となる身のこなしも軽やかで指示も的確でスピード感があります。体験した競技は「アルティメット」です。子どもたちも初めての競技へのワクワク感から授業の魅力にすぐ引き込まれ、存分に授業を楽しみました。また授業後は質問に答えてもらう場を設けてもらい、子どもたちも中学校生活に向けてもっていた不安が、少しづつ解消され、安心したようでした。