少し暖かさを感じる中で、今日は綱引きと加太ソーランの練習をしました。初めての運動場での全校練習でした。子どもたちは自分の立つ場所や進行方向を確認しながら、真剣に練習していました。6年生が1年生に声をかける姿が、よく見られました。

























少し暖かさを感じる中で、今日は綱引きと加太ソーランの練習をしました。初めての運動場での全校練習でした。子どもたちは自分の立つ場所や進行方向を確認しながら、真剣に練習していました。6年生が1年生に声をかける姿が、よく見られました。
























10月25日、少し早いハロウィーンをみんなで楽しみました。それぞれにお面をつけたり帽子をかぶったりして、仮装して体育館に集まりました。児童会の進行で、はじめに「♪ Head Shoulder ~ ♪」の歌に合わせて、みんなで踊りました。





そして、英語専科とALTの先生がハロウィンにまつわるクイズを出してくれました。カボチャや合言葉を答える難問?に、子どもたちは集中して聞きながら手を挙げていました。









最後は「カボチャレース」でした。ラケットにカボチャを載せて、カラーコーンを回ります。時々カボチャを落としてしまう子もいましたが、元気な応援の声に励まされて、笑顔でゴールしていました。

















ハロウィン集会を楽しんだ後は、「Trick or Treat」と言いながら、校長室と職員室を回りました。そこでも英会話を楽しんでいました。子どもたちが英語やゲームなどの異文化を楽しんでいる様子が見られてよかったです。ハッピー ハロウィーン!












運動会の練習が始まり、1回目の今日は「加太ソーラン」の練習をしました。はじめにたてわり班に分かれて、それぞれの場所で練習しました。後半は全員が体育館に集合し、振り付けを確認しながら踊りました。1年生も高学年に教えてもらいながら少しずつ振り付けを覚えてきました。
これから毎日、運動会の練習があります。熱中症の心配はありませんので、間隔を取りながら思いきり身体を動かして、体力増進にも努めたいと思います。














10月22日、昼生小学校の学校運営協議会関係の方々が、本校の複式学級の算数の授業を視察されました。3・4年生と5・6年生の算数の授業では、教員が2学年にそれぞれ課題を示し、子どもたちが自主的に解いたり発表し合ったりする「わたりの授業」を行っていました。
授業後は、複式学級の良さや課題等を説明し、今後の学校運営協議会の活動等について交流しました。








6年生は、食物にふくまれている栄養素の役割を学習し、給食のリクエスト献立を考えていました。すべての栄養素がふくまれるようにメニューを工夫していました。どの献立に決まるか楽しみです。
5年生は、理科の授業で、砂場に実際に蛇行した川を作って水を流し、浸食や氾濫の様子を観察しました。その様子を動画に撮り、ふりかえりで活用しました。地形のちがいで川の水の流れが変わることも確認していました。























板屋の信号や体育館前で、地域の方が子どもたちに「おはようございます」と元気に声をかけてくださいました。子どもたちは、はずかしそうにしながら挨拶を返していました。いつも見守っていただきありがとうございます。







10月20日5限目に、児童会選挙がありました。はじめに5・6年生の立候補者が演説をしました。「あいさつのできる学校にしたい」「ちくちく言葉をやめてふわふわ言葉があふれる学校にしたい」「ドッジボールだけでなく、みんなで遊べる遊びをいろいろ考えたい」など、一人ひとりがしっかり考えて話していました。投票する方も、演説をよく聞いて真剣に投票していました。

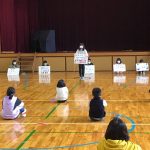









10月18日、気温が下がり、加太小学校でも長袖姿の児童が増えました。
今日は、英語の授業があって、3~6年生がカードを使ったりゲームをしたりしながら、英語を楽しく学んでいました。
体育の授業では、1・2年生がマット運動をしていました。何回も練習するうちにじょうずに回れるようになっていました。また5・6年生が高跳びをしていました。自分のベスト記録が出せるようがんばっていました。

























