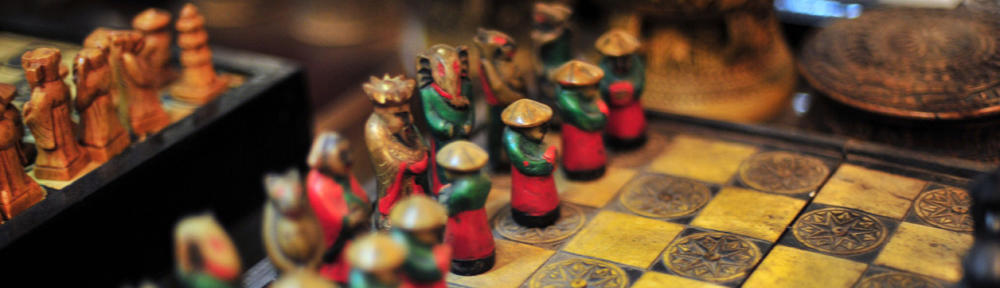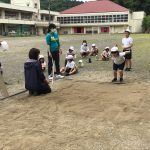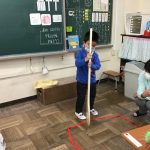6年生対象に民生委員児童委員による授業が行われました。民生委員児童委員の主な仕事やどんな願いをもってみえるのかなど、直接お話を聞きました。そして、民生委員児童委員の仕事内容がよくわかるように紙芝居も見せていただきました。最後に、子どもたちは、「自分が生まれ育った加太が好きな大人になってほしい」「困った人がいたら手を差し伸べることができる大人になってほしい」「みんなの役にたてる大人になってほしい」などと民生委員児童委員の方からメッセージももらいました。大人も子どもも同じ地域に住んでいる人が、お互いをよく知り、つながり合うことの大切さを改めて感じることができました。