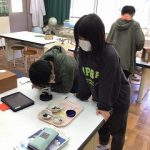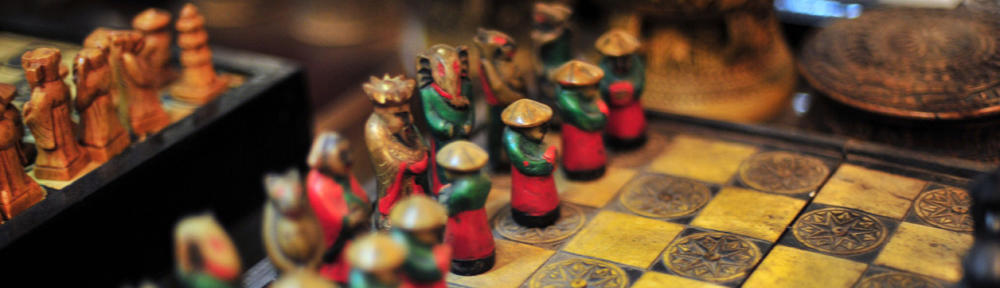6年生の理科では「大地のつくりと変化」の学習をしています。残念ながら加太小学校周辺には地層を観察することができる場所がないため、教科書やインターネットの写真、NHK for schoolを活用し、様々な地層の写真を見ることから、地層に興味・関心を持つように学習しています。
5年生の理科の授業を思い出し、地層がしま模様に見えるのは、川の流れによって1つ1つの層が、れき、砂、泥などのつぶの大きさの違う土や、色の違う土でできているためであることに関連付けていきます。また、地層の中には化石が含まれる場合があることや、火山灰でできた地層があることで、その成り立ちの違いについても学習していきます。
今回の授業では、身の回りにある砂と火山の噴火でできた火山灰の成り立ちが違うことに着目し、火山灰にはどのような特長があるのか、火山灰と砂を顕微鏡で観察しました。水で火山灰をよく洗ってペトリ皿に移した後、顕微鏡で観察するとともに、タブレットで撮影して、記録活動も行いました。児童からは、「火山灰には角ばっているものが多く、ガラスのように透明なものもあった。」「火山灰は水のないところでも降り積もることがあるし、火山や地震の活動は様々な土地の変化をもたらすことが分かった。」などの意見がありました。